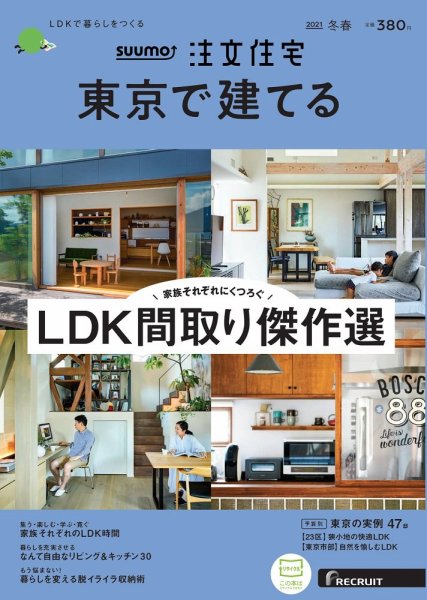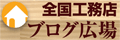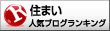東京で家を建てるならRCdesign
くもり時々晴れの東京です。
そんな今日は朝からお問い合わせ対応、社内ミーティング、渋谷区西原計画検討、資材発注、材料メーカーさんと電話、北区赤羽西計画検討、杭屋さんと電話、杉並区阿佐ヶ谷北2丁目計画検討、見積作成、文京区白山計画のお客様とお電話、杉並区今川計画検討など。
午後は資料作成、図面作成、7丁目のお客様と連絡、板金屋さんと電話、杉並区高円寺南計画検討、図面作成、世田谷区新町計画検討など。夕方は構造担当と電話、資料作成、お問い合わせ対応、ミーティングなど。
キンモクセイの第2波が匂っていますね。
ではこちら。
住所に使われる「地番」「住居表示」の違いをご存知ですか まったく異なるルールの書き表し方
「番地」と「番・号」。どちらも住所を書くときに使いますよね。この二つ、どのような違いがあるかご存知ですか。実はそれぞれまったく異なったルールの書き表し方なんです。
なるほど。
この辺りも日本特有のややこしい風習が残っているものの一つかもしれませんね。
一般的には住居表示が使われていて、いわゆる住所として常用されているものがそれです。
一方で地番というのは、土地の売買や課税対象などの時に目にするもので、日常では特に意識するものではないかもしれません。
誰それさんが持っている土地のひと区画(一筆、二筆と数えます)を1番地、その隣の誰それさんの土地ひと区画(一筆)を2番地、というふうに決めて、番号を振っていったものです。これは法務局(登記所)が定めたもので、「地番」といいます。いまも登記簿などには、この地番が使われています。
一方で、より実用的に使えるように登場したのが「住居表示」という新しい住所の表し方です。
比較的人の多い市街地では、すでに住居表示が使われていると思いますが、住居表示は現在、日本全国で導入されているわけではなく、未実施のエリアではいまも「番地」が使われている場所もあるようです。
「地名地番」と「住居表示」の違いはご理解いただけましたでしょうか?お間違えの無いようにご注意くださいね。
それでは。
今日もありがとうございます。

人気ブログランキング ←お力添えを是非!
くもり時々晴れの東京です。
そんな今日は朝からお問い合わせ対応、社内ミーティング、渋谷区西原計画検討、資材発注、材料メーカーさんと電話、北区赤羽西計画検討、杭屋さんと電話、杉並区阿佐ヶ谷北2丁目計画検討、見積作成、文京区白山計画のお客様とお電話、杉並区今川計画検討など。
午後は資料作成、図面作成、7丁目のお客様と連絡、板金屋さんと電話、杉並区高円寺南計画検討、図面作成、世田谷区新町計画検討など。夕方は構造担当と電話、資料作成、お問い合わせ対応、ミーティングなど。
キンモクセイの第2波が匂っていますね。
ではこちら。
住所に使われる「地番」「住居表示」の違いをご存知ですか まったく異なるルールの書き表し方
「番地」と「番・号」。どちらも住所を書くときに使いますよね。この二つ、どのような違いがあるかご存知ですか。実はそれぞれまったく異なったルールの書き表し方なんです。
大阪梅田一番地?
「は〜ん〜し〜ん〜 は〜ん〜し〜ん〜 大阪梅田一番地♪」という歌が昔ありました。阪神百貨店のテレビコマーシャルです。そうなんですね、あの阪神百貨店があった場所がその頃、大阪市北区梅田の一番地だったのですね。おそらく、たぶん、ですが。
2021年10月3日 16時30分 まいどなニュース
2021年10月3日 16時30分 まいどなニュース
なるほど。
この辺りも日本特有のややこしい風習が残っているものの一つかもしれませんね。
一般的には住居表示が使われていて、いわゆる住所として常用されているものがそれです。
一方で地番というのは、土地の売買や課税対象などの時に目にするもので、日常では特に意識するものではないかもしれません。
誰それさんが持っている土地のひと区画(一筆、二筆と数えます)を1番地、その隣の誰それさんの土地ひと区画(一筆)を2番地、というふうに決めて、番号を振っていったものです。これは法務局(登記所)が定めたもので、「地番」といいます。いまも登記簿などには、この地番が使われています。
ただ、記事にもありましたが、この「番地」というのは、その町名のエリアにある土地一筆ごとに番号が振られますから、これがもし面積の広い町だったりすると「15864番地」とか、やたらに数が大きくなってしまうことがあります。
また、そもそも土地というものは整然と並んでいませんし、番地の振り方にもルールがはっきりしない部分もあって、特に住宅の密集している市街地などでは、その番地を探すのが大変ということもあります。
また、そもそも土地というものは整然と並んでいませんし、番地の振り方にもルールがはっきりしない部分もあって、特に住宅の密集している市街地などでは、その番地を探すのが大変ということもあります。
一方で、より実用的に使えるように登場したのが「住居表示」という新しい住所の表し方です。
住居表示というのは、1962年5月10日に施行された「住居表示に関する法律」に基づくものです。
こちらも記事にありましたが、たとえば道路とか川とかで区切られた土地のひとかたまり、ひと区画ごとに「1番」「2番」と番号を振っていきます。これを「街区符号」といいます。
次に、その区画の周囲のどこかを起点にして、そこを「1号」と決めます。その後は右回りに、10メートルから15メートルごとに「2号」「3号」と「住居番号」を振っていきます。そして、その建物の「住所」は、「出入り口の場所」で決まります。
次に、その区画の周囲のどこかを起点にして、そこを「1号」と決めます。その後は右回りに、10メートルから15メートルごとに「2号」「3号」と「住居番号」を振っていきます。そして、その建物の「住所」は、「出入り口の場所」で決まります。
比較的人の多い市街地では、すでに住居表示が使われていると思いますが、住居表示は現在、日本全国で導入されているわけではなく、未実施のエリアではいまも「番地」が使われている場所もあるようです。
「地名地番」と「住居表示」の違いはご理解いただけましたでしょうか?お間違えの無いようにご注意くださいね。
それでは。
今日もありがとうございます。

人気ブログランキング ←お力添えを是非!